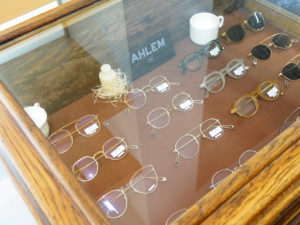簡単に言うと、物を見る時のピント量と目の内寄せ量との関係の話です。
はじめに
- 調節につて
- 輻輳について
- 調節と輻輳の関連(調節性輻輳)について
- AC/A比(AccommoditevCnvergennce/Accommodation)について
お話してまいりたいと思います。
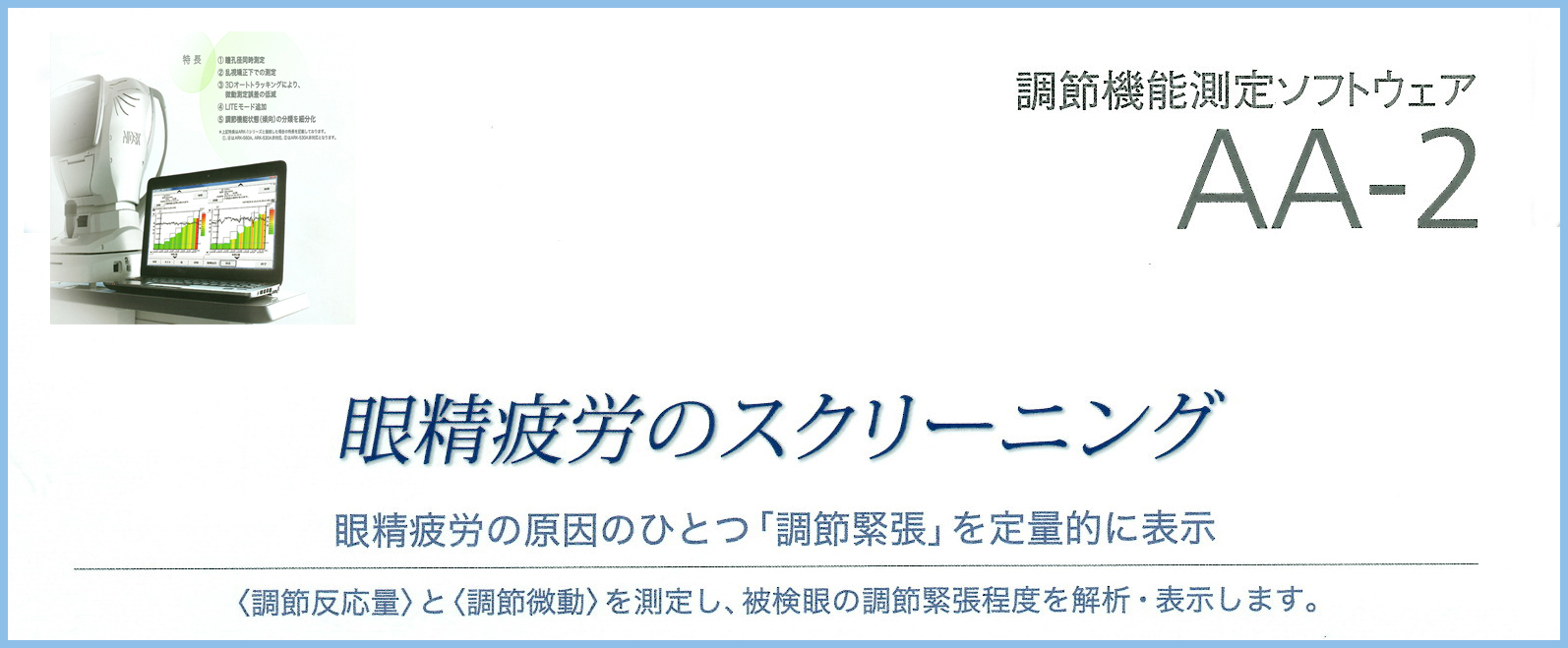
調節について
■調節
眼の調節とは、眼の中にある水晶体というレンズがその厚さを変えることで屈折力を増減すことです。ちなみに私たちは、遠くの物を見るときは水晶体を薄くし屈折力を減じピント合わせ、近くの物を見るときは屈折力を増してピント合わせをしています。
■調節刺激と調節反応
眼前にある視物に焦点を合わせる事を要求する視性刺激を調節刺激と言います。たとえば眼前40cmにある視物に焦点を合わせようとすると調節反応として2.5デオプターの調節をすれば良いわけです。しかし、実際には、調節刺激と調節反応とが釣り合わず調節力が少なかったり、逆に多かったりする事があります。
■調節と調節域(正視眼の場合)
眼の前にある視物を見ようとしたときの距離と調節との関係は
調節力(ディオプター)=眼から視物までの距離(単位:メートル)/1
- 1ディオプター=1m(眼前1メート前にある物を見る時の必要調節力)
- 2ディオプター=0.5m(眼前0.5メート前にある物を見る時の必要調節力)
- 2.5ディオプター=0.4m(眼前0.4メート前にある物を見る時の必要調節力)
■調節異常の分類
- 調節不全(Accommodative insufficiency)
- 調節衰弱(ILL-sustained accommodation)
- 調節麻痺、調節無力症(Accommodative in facility(inertia))
- 調節緊張、調節痙攣(Accommodative excess(spasm))
調節異常の症状
- 調節力低下タイプ(不全。衰弱)
- 近業作業時にぼやけ、
- 頭痛、
- 眼精疲労、
- 複視、
- 読書困難、
- 視線移動に伴うピント合わせ不良、
- 眩輝感、
- 調節反応不良、
- 上記症状視線移動に伴うピント合わせ不良、
- 調節緊張タイプ(緊張、痙攣)の症状と近業作業後のぼやけ(遠見、近見とも)
調節障害への対処方
- 遠視、弱度乱視、不同視の矯正
- プラスレンズ処方
- 調節機能不全調節衰弱に有効
- 調節緊張には一般的には有効ではない
- Vision training 反応不良で有効
■調節と老視
老視の定義を加齢による調節力の衰えに起因する近見不良とするか単に加齢による調節力の衰えとするかで話が変わります。例えば正視で45才のAさんは調節力が衰え手元の細かい文字が見にくいと言っています。ところが同じ45才でも-1.50Dの近視のBさんは見にくくはないと言いと言っています。さて調節力は年齢に比例して減退しているはずなのでAさんもBさんも老視なのか、そうではなく手元の細かい文字が見にくいと言っているAさんだけなのか?
筆者は、AさんもBさんも老視になってると考える派です。たまたまBさんは近視の分だけ調節力が少なくて済むので裸眼で手元が見えるのです。証拠に近視のメガネを掛けるとAさんとほぼ同じく見にくくなるはずですから。

輻輳について
■輻輳
両眼視が最適に行われる為には見たい物に両目の視線が合っていないといけません。遠くにあるもと近くにあるものとではピント合わせ(調節)と視角(輻輳角)を変えなければなりません。輻輳とは平たく言うと寄り眼の事です。見たい距離分眼が内寄せしていれば問題ないのですが、両眼視検査をしてみると意外にそうではないのが解ります。
輻輳には
- 緊張性輻輳 tonic convergence
人の解剖学的安静位はやや外斜位の状態にある。これを左右各眼が無限遠へ平行して向かう眼位へ寄せてくる輻輳 - 調節性輻輳 accommodative convergence
調節しようとする意図に付随して生じる輻輳(各人一定の比率で輻輳が生じるAC/A比で現す事が出来る)
- 融像性輻輳 fusional convergence
輻輳が他の輻輳で不十分な場合に両眼の網膜からの像を一致させようととして随意的に生じる輻輳で運動性融像ともいわれている。
- 近接性輻輳 proximal convergence
視物が近くにあるという感覚により、心因的に不随意に生じる輻輳
■輻輳異常の分類には
- 融像性輻輳機能不全(Fusional vergence dysfunction)
- 輻輳不全(Convergence insufficiency)
- 偽輻輳不全(Pscudo convergence insufficiency)
- 輻輳過多(Convergence excess)
- 開散不全(Divergence insufficiency)
- 基本型外斜位(Basic exphoria)
- 基本型内斜位(Basic esophoria )
■輻輳障害への対処方法
- ビジョントレーニング(Vision Training)
- プリズムメガネ
■調節性輻輳
輻輳運動は両眼に視差のある像が投影されたときにに生じると言われています。また眼前の視物が近づいて来ることにより網膜像がボケる事で調節が喚起されると考えられています。調節に伴って起こる輻輳を調節性輻輳と呼んでいます。
■AC/A比(Accommoditev Cnvergennce/Accommodation )
調節と輻輳の間には密接な関係があります。
調節性輻輳とは調節刺激に喚起され輻輳が生じる事を言いますが、その調節性輻輳の大きさと調節刺激の強さの比をAC/A比で表したものです。
検査法としては
- Heterophoria法=視標の距離を変えることで調節刺激を与え眼位の変化を求める方法
- Gradient法=一般に視標の距離を45cmにし眼前にレンズを付加しその前後の眼位変化を求める方法
があります。AC/A比から楽に見えるメガネを作る為に度数を微調整する事があります。